願い事をしながらその鏡を磨くと願いが叶うという。
ヴェネツィアで作られた大きな楕円形のその鏡は、ガラスの片面にメッキを施したものではなく、金属の表面を磨き上げて作られたもの。
磨かなければすぐに酸化して曇ってしまう。
磨くと願いが叶うが、その代償として大切なものを失ってしまう魔性の鏡でもあった。
秋吉理香子さんの『鏡じかけの夢』を読みました。
あらすじ
何世紀も前にヴェネツィアで作られたというその金属の鏡は、願い事をしながら磨くと願いが叶うという。
しかし、鏡はいろんな角度に反射するため、願ったとおりに実現することは限らないらしい。
精神科病院に入院した華族の女性を献身的に看護する看護婦、金属の鏡の鏡研ぎをする職人、関東大震災で全身に火傷を負い耳と言葉を失いながらも財を築いた男…
鏡は所有者の間を転々としながら、人の願いを叶え、没落させていく。
感想
これまで読んだ秋吉理香子さんの作品とは、ちょっと違った印象を受けました。
文体を変えて、引き出しを増やす試みをされたのかな?
ジャンル的には秋吉理香子さんお得意のイヤミスになるのかと思いますが、ミステリ色は弱いと思います。
5編の掌編からなる連作短編集と見るのが普通かも知れませんが、私は1つの長編と見た方が良いのでは?と感じました。
最後の『双生児の鏡』まで読むと、私の言いたいことがわかっていただけるかと。
2つめの『ナルキッソスの鏡』の中で、ガラス製の鏡だとどんなに鏡像に近づこうとしてもガラスの厚みが邪魔をして直接触れることができないが、金属鏡の場合は鏡像に直接触れることができる。といった記述が出てきますが、誰もが1度は体験したことがある話ではないでしょうか。
実用できる状態の金属鏡を見たことはありませんが、金属鏡が特別なものだと感じさせられた記述でした。
願い事が叶えば、その分だけ不幸になる。
差し引きゼロということなのでしょうが、大きな願いが叶うと、それだけ不幸になり…
そこまで!と、秋吉理香子さんの容赦ない筆に驚かされっぱなしでした。
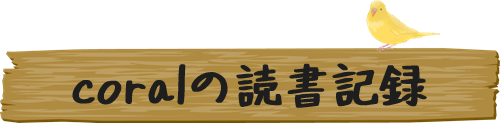
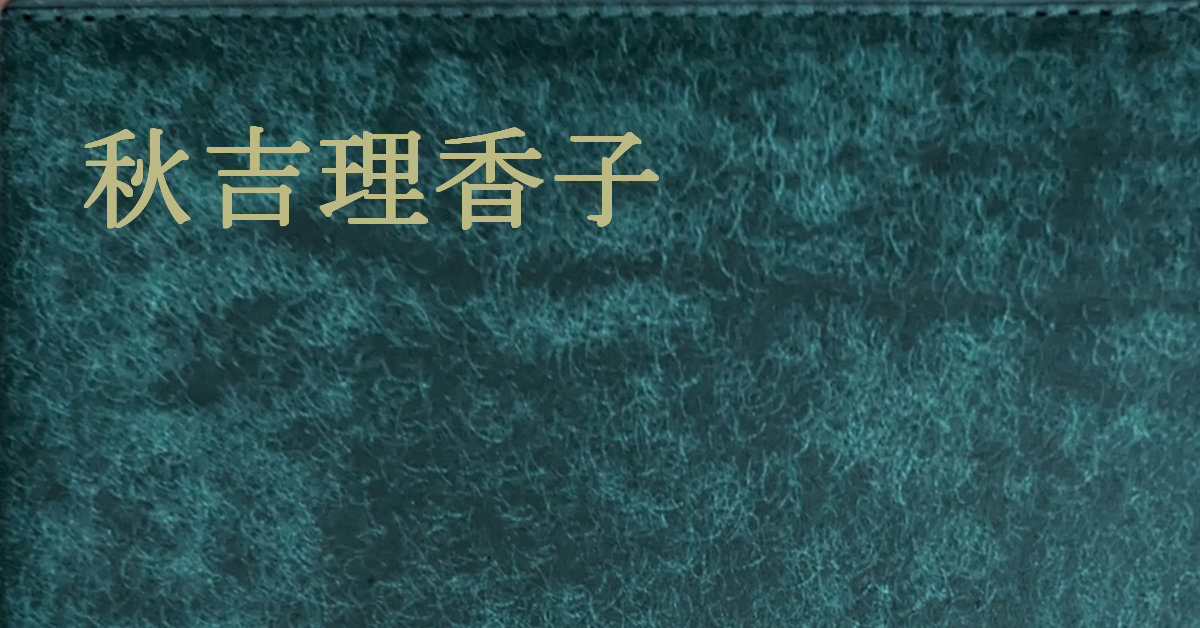





コメント