「模写は、日本画の古典研究の代名詞と言えます」
芸大の油画科の学生・稲葉真は、同じ大学の大学院文化財保存修復専攻・保存修復日本画研究室の人見教授の言葉を聞いてがっかりした。
真の父は日本画家だったが、次第に古典絵画の模写や日本画研究にのめり込み、名を残せなかった画家だったからだ。
従兄の凛太郎が休学中の真に持ってきたのは、江戸時代の襖絵の修復模写制作の話だった。
愛野史香さんの『あの日の風を描く』を読みました。
あらすじ
美大の油画科を休学中の稲葉真は、江戸時代に祇園で書画屋を営んでいた日下部家に残る襖絵の復元模写制作を手伝うことになった。
襖絵を描いたのは、父が狩野派を破門された清原雪信の娘・平野雪香。
日下部家の蔵に保管されていた襖絵は、シミや退色、破れなどが酷く、枚数も足りない。
真は保存修復研究領域の修士二年生、土師俊介と蔡麗華とともに、作業をはじめる。
感想
とんでもない作家さんと出会ってしまったかも知れません。
2024年の第16回「角川春樹文学賞」を選考委員満場一致で獲得したという、愛野史香さんのデビュー作ですが、終始圧倒されっぱなしでした。
江戸時代の襖絵を復元模写するという話なのですが、日本画の歴史、流派、画法、画材、修復や模写の仕方などが事細かに書かれています。
一歩間違えると、マニアックすぎて一般人には理解できない世界の話になってしまうところですが、私のような日本画にまったく縁のない人間でも容易についていけるようになっています。
日本画家だったが、次第に個人制作をしなくなり、故人の作品の研究や模写ばかりを遺した父のことを理解できないでいる真が、襖絵の修復模写を通して父のことを見直していく姿も細やかに描かれています。
修復模写を行うためには、襖絵が置かれていた場所や環境を理解し、絵師の気持ちになりきり、筆さばきを再現する必要が…
さらに、欠けているところに何が書かれていたかを想像し、再現する作業も、答えがないだけに難しい作業です。
特に、夏の襖に描かれていた鳥と、その姿勢について解を示されたときには、解釈が見事すぎて思わず声が出てしまいました。
こうやって聞くと、自由に絵を書く方が遙かに簡単そうに思えてきます。
もちろん、どちらも特有の難しさがあるのでしょうが、個人制作をするのも、模写をするのも、優劣つけがたいことなんだということがわかります。
最後に12面の襖絵が完成したときには感動。
完成した絵が脳裏に浮かんだわけでもなく、頭の中は空っぽなのですが、それまでの苦労や努力が形になったということで、目に見えないものに圧倒されてしまいました。
その直後、襖絵の描写があり、和室の中央に立っているかのような気持ちになりました。
ストーリーも素晴らしいのですが、読み手が次に知りたいことがわかっているかのような展開。
これは、天性のものだと思います。
早くも次の作品が待ちきれないでいます。
オススメです!!
ちなみに、愛野史香さん、当然芸大卒なんだろうなって思ったら、薬学部卒の薬剤師さんでした!
名古屋城の本丸御殿の障壁画を見て、どういう人が復元しているんだろう?と思ったことが、この作品に繋がったそうです。
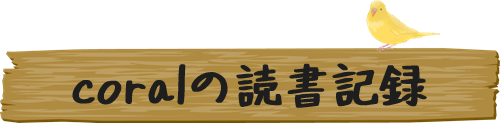
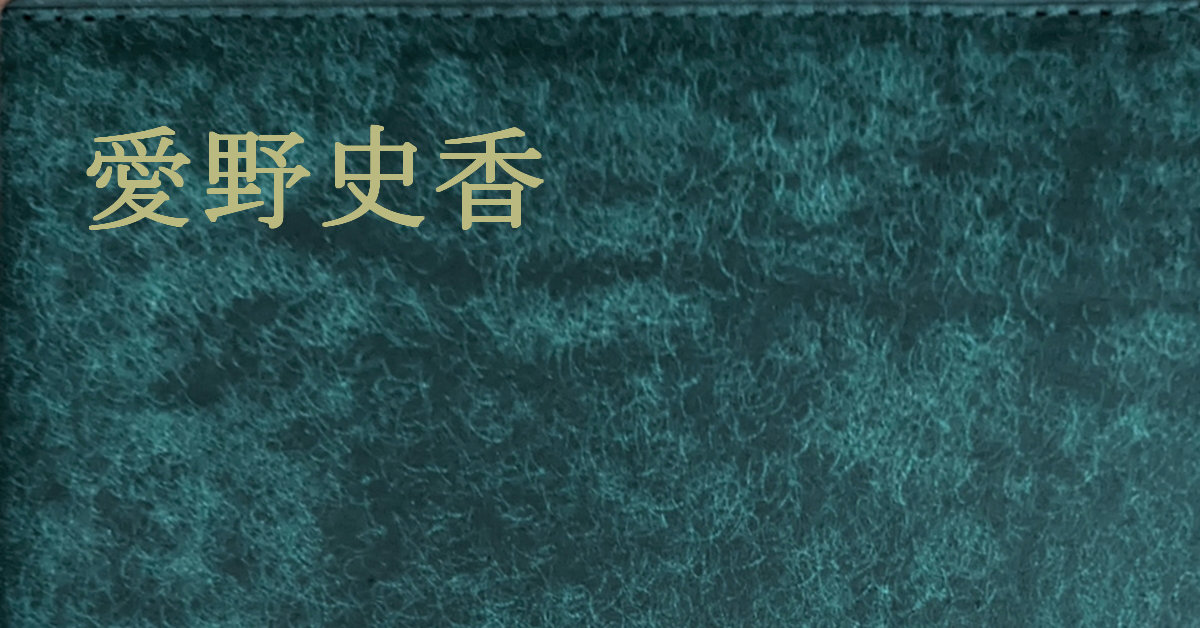





コメント